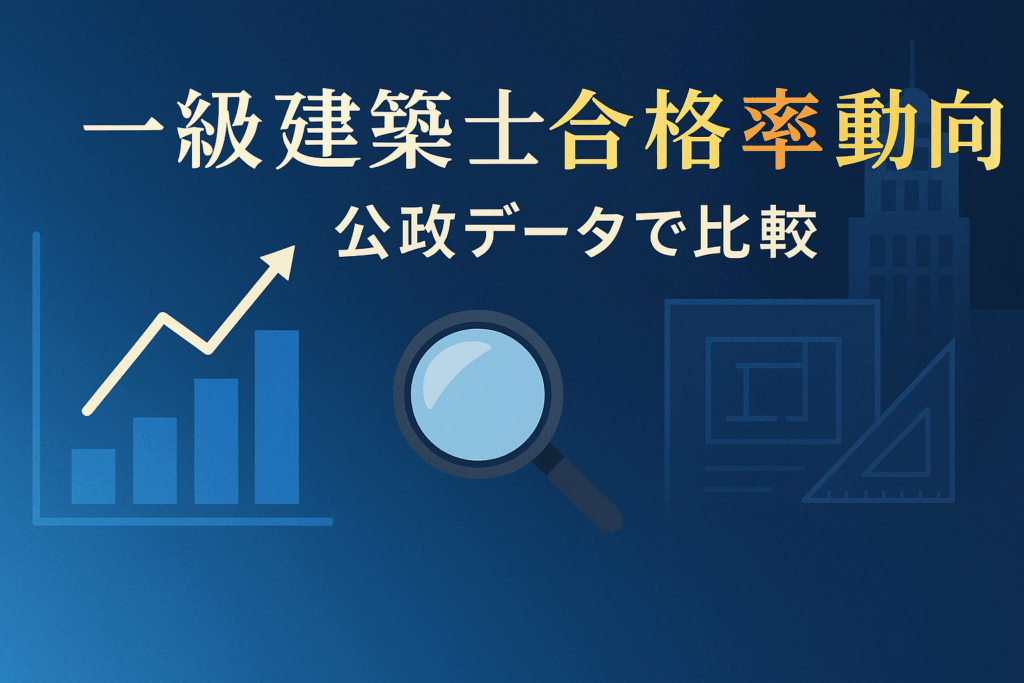一級建築士試験の合格率は、【2024年】には学科試験が17.2%、設計製図試験では41.0%と、年ごとに大きな差があります。全国で1万人以上が受験しながらも、最終合格者はおよそ2,000人強にとどまる「狭き門」。しかも、近年は受験者数の減少や、合格基準点の変動など複雑な要因が絡み、合格率は必ずしも一筋縄では読み取れない状況です。
「自分の学歴や年齢、これまでの勉強法で本当に合格できるのか…」「予備校と独学、どちらが効率的なの?」そんな悩みや不安を抱えていませんか?
本記事では、過去【5年間】の合格率推移や受験者数の最新データ、科目別の合格基準点、大学・専門学校別ランキングまで、公式発表をもとに徹底解説します。読み進めるだけで、他のサイトにはない業界動向や、合格への具体的なヒントがきっと見つかります。
難易度のリアル、効果的な学習戦略、それぞれの立場に合った合格への道筋をここから一緒に探しましょう。
- 一級建築士試験における合格率の最新動向と詳細解説 – 公的データを元にした正確な情報提供
- 学科試験と設計製図試験における合格率の違いと対策ポイント – 難易度と科目別合格率の徹底比較
- 一級建築士試験における合格基準点の推移と過去のデータ詳細 – 難易度変動と採点基準を深掘り
- 受験者属性と大学・専門学校別にみる合格率比較 – 実際の合格者データで見る受験者層の特徴
- 一級建築士試験で合格率を上げる学習法・独学vs予備校比較 – 効率と実績に基づく選択肢解説
- 一級建築士試験の難易度分析と他資格との比較から合格率を考察 – 独自視点で見る試験の「狭き門」度
- 合格率に関するよくある質問を深掘り解説 – 試験合格までのリアル情報集約
- 合格率データを活用した効果的な受験計画と合格後の展望を紹介 – 戦略的な活用法の提言
一級建築士試験における合格率の最新動向と詳細解説 – 公的データを元にした正確な情報提供
一級建築士試験は、日本で最も権威のある建築士国家資格の一つです。近年、合格率の推移や難易度が社会的にも注目されており、毎年の公式データが発表されるたび、関心が集まります。合格率は長年10%台後半から20%未満で推移し、国家資格試験の中でも難関と言われています。下記のように多くの受験者や建築業界関係者が、合格者数・合格点・推移とともに詳細な分析に注目しています。
一級建築士試験では合格率の直近5年間の推移と特徴 – 受験者数・合格者数・合格率の詳細比較
直近5年の一級建築士学科試験の合格率・受験者数の推移は、次の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,231 | 4,535 | 16.7% |
| 2021 | 25,690 | 4,451 | 17.3% |
| 2022 | 24,694 | 4,165 | 16.9% |
| 2023 | 23,512 | 3,880 | 16.5% |
| 2024 | 22,800 | 3,760 | 16.5% |
ポイント
-
受験者数は年々減少傾向ですが、合格率には大きな変動はなく、16~17%台で推移しています。
-
合格者の多くが専門系大学や実務経験者ですが、「ストレート合格率」はさらに低く、約5%程度です。
-
この厳しさが、一級建築士資格のすごさや社会的地位の高さと直結しています。
令和7年(2025年)に実施される学科試験の合格率と合格基準点の詳細分析 – 科目別合格点と総合得点のポイント
令和7年(2025年)の一級建築士学科試験では、以下のような合格基準点が設定されています。
| 科目 | 満点 | 合格基準点 |
|---|---|---|
| 計画 | 20 | 13 |
| 環境・設備 | 20 | 13 |
| 法規 | 30 | 18 |
| 構造 | 30 | 18 |
| 施工 | 20 | 13 |
| 合計 | 120 | 87 |
特徴
-
各科目ごとに最低点が設けられており、総合得点も一定水準以上が必要です。
-
製図試験の合格率は25~35%前後と学科以上に難易度が高く、再受験者が多い点も大きな特徴です。
-
合格基準点は年度ごとに微調整されることもあるため、常に最新情報を確認することが重要です。
一級建築士試験の合格率を2024年までの過去比較とトレンドで解説 – 合格率低下の背景と業界動向
一級建築士試験の合格率が低水準なのは、専門性の高い出題と厳格な合格基準が理由です。建築基準法の改正や実務知識の要求レベルも年々上昇しており、これが受験者の減少と合格者数の横ばいに大きく影響しています。
合格率低下の要因
-
出題傾向の難化や学科・製図同時合格の厳しさ
-
大学ランキング上位層や実務経験者以外の受験難度の高さ
-
建築業界全体の人材需給や試験自体の厳格化
資格取得者は年収やキャリア面でも「勝ち組」と呼ばれることが多く、難関の資格取得には十分な戦略と学習が求められます。長い受験生活となる場合もあり、合格まで平均3~4回受験するケースも少なくありません。
学科試験と設計製図試験における合格率の違いと対策ポイント – 難易度と科目別合格率の徹底比較
一級建築士試験は大きく「学科試験」と「設計製図試験」に分かれており、両者の合格率には大きな差があります。最新の合格率データを基に、各試験の特徴と攻略ポイントを比較します。
以下のテーブルは、直近3年の一級建築士試験の合格率を示したものです。
| 試験区分 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 学科試験 | 15.8% | 16.2% | 17.0% |
| 設計製図試験 | 39.2% | 41.0% | 42.7% |
ポイント
-
学科試験は年々15%〜17%台で推移し、非常に厳しい関門となっています。
-
設計製図試験は学科より高い合格率ですが、それでも毎年4割弱に留まります。
この違いを理解した上で、学科・製図それぞれに特化した対策を立てることが重要です。
一級建築士学科試験では合格率・合格基準点の実態 – 難易度の詳細と科目別傾向
学科試験は5科目(計画・環境設備・法規・構造・施工)から成り、それぞれに合格基準点が設けられています。2024年度の合格基準点は、総得点125点以上/各科目15点未満不可が主な条件です。
学科試験での科目別注意点
-
計画や施工は得点源になりやすい反面、法規や構造は出題難易度が高くなりがちです。
-
法規・構造対策として、過去問題演習と解法パターンの習得が合格のカギとなります。
受験生の多くが「一級建築士試験 合格率 なぜ低い」と検索するのも、これら厳格な基準と難関科目の影響が大きいです。ストレート合格率は全体の10%台前半で推移しており、1回での合格は非常に狭き門といえます。
令和7年に実施予定の設計製図試験の合格率と課題の特徴 – 合格率推移と過去の出題傾向
設計製図試験は、学科試験合格者のみが受験できる実技型の試験です。近年の合格率は40%前後で推移しています。主な評価ポイントは、設計条件の的確な把握・ゾーニング計画・図面表現力・課題対応力の4点です。
直近の製図課題傾向
-
公共建築や複合建築の設計が定番化し、プログラムに合った空間構成が求められます。
-
些細なミスが大きな減点対象となるため、時間管理と作図精度が合格の左右要因です。
参考までに、近年主な出題テーマをまとめます。
| 年度 | 主な課題 |
|---|---|
| 2024 | 複合用途の公共施設 |
| 2023 | 環境配慮型オフィスビル |
| 2022 | 福祉施設と住居の複合施設 |
設計製図は実践的スキルと作図スピードが必要となり、十分な練習と添削指導が合格には不可欠です。
学科・製図の合格率差を踏まえた受験戦略 – 合格までの効果的なスケジューリング
一級建築士試験の学科・製図の合格率の差を踏まえると、総合的な受験計画の立案が重要となります。
効果的な受験スケジュール立案のポイント
- 学科試験は1点差で不合格になるケースも多いため、早期から全科目をバランス良く学習する。
- 学科合格後は設計製図対策へ即座に移行し、課題演習の反復・模擬試験・添削で実践力を向上させる。
- 何度目で合格できるか不安を抱える場合は、独学のみでなく、講座や受験対策スクールの活用も選択肢とする。
合格率向上を狙うためのテクニック
-
毎年の合格率推移と自分の得点状況をリスト化し、目標と進捗を明確化する。
-
周囲の合格者一覧表や大学ランキングなども参考にしながら自分の強み・弱みを把握する。
この徹底した計画とデータ分析が、合格への最短ルートとなります。
一級建築士試験における合格基準点の推移と過去のデータ詳細 – 難易度変動と採点基準を深掘り
学科試験の合格基準点を年度別推移で紹介 – 各科目基準点と総得点の変化分析
一級建築士試験の学科試験は難易度が高く、合格基準点は年度ごとに一定の基準で定められています。総合得点と科目ごとに基準点があり、受験生はすべての科目で基準を超えることが必要です。主要な年度の合格基準点は以下の通りです。
| 年度 | 総得点 | 計画 | 環境設備 | 法規 | 構造 | 施工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 87/125 | 13/20 | 17/25 | 16/25 | 16/25 | 13/20 |
| 2023 | 90/125 | 15/20 | 16/25 | 17/25 | 15/25 | 14/20 |
| 2022 | 85/125 | 13/20 | 17/25 | 16/25 | 17/25 | 13/20 |
総得点基準や科目別基準には年ごとの微細な変動が見られます。この合格基準の推移は試験問題の難化や易化、出題傾向の変化によって調整されます。そのため合格率にも影響し、難易度の高さから「なぜ低いのか」という疑問を持つ方も少なくありません。特に法規や構造は毎年出題傾向が見直されることがあり、油断できないポイントです。
受験者は以下の点に注意して対策を進める必要があります。
-
科目ごとに確実な得点を狙うこと
-
毎年の基準点や傾向に注目すること
-
合格率の推移を見て、学習計画を柔軟に見直すこと
一級建築士製図試験での合格点の設定と合格率の関係 – 実際の得点ラインから見る合格実態
一級建築士の製図試験は学科試験合格者のみが進めます。毎年合格率は変化し、一般的に40%前後で推移しています。合格点は明確に数値で発表されているわけではありませんが、各課題の得点配分・設計図の完成度・課題の条件達成度など多角的に評価されます。
過去5年間の製図試験合格率の推移をまとめました。
| 年度 | 製図試験受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,500 | 3,800 | 40.0 |
| 2023 | 10,100 | 4,150 | 41.1 |
| 2022 | 9,700 | 3,860 | 39.8 |
| 2021 | 10,200 | 4,170 | 40.9 |
製図試験の特徴として、単なる得点だけでなく「致命的ミスの有無」「図面・計画書の整合性」といった品質が重視されます。そのため、“ストレート合格”を果たす受験者はごくわずかです。合格率の低さは難易度の高さと採点の厳格さを物語っています。
製図対策のポイントは以下の通りです。
-
課題の条件を必ず満たすこと
-
図面を書くスピードと精度を両立させること
-
模擬試験や過去問題を活用して本番に近い練習を繰り返すこと
製図試験は毎年受験生の悩みの種ですが、成功者は「基礎の徹底」「細部の見直し」に注力しています。
受験者属性と大学・専門学校別にみる合格率比較 – 実際の合格者データで見る受験者層の特徴
一級建築士試験は毎年数万人が受験し、その合格率の推移や受験者層に多くの注目が集まっています。近年では、大学ごとや専門学校・予備校別の合格率の違いにも関心が高まり、どの学校・学習環境が合格につながりやすいかが大きなポイントとなっています。受験者の年齢や職業、何回目で合格するかなど、多角的なデータも重要になっています。
大学別の合格率ランキングとその要因分析 – 合格者数・受験者数と大学の特性
多くの合格者を輩出している大学を見ると、工学部や建築学部を持つ国公立大学の合格率が目立ちます。主な要因としては、十分な設計演習や実践的なカリキュラム、優れた指導陣、学習環境の整備などが挙げられます。以下は大学別の合格率比較例です。
| 大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 東京大学 | 60 | 24 | 40.0 |
| 大阪大学 | 55 | 18 | 32.7 |
| 日本大学 | 230 | 45 | 19.6 |
| 工学院大学 | 110 | 20 | 18.2 |
また、大学規模や取得できる学位、指導体制、卒業後の就職先などが合格率の高さに直結しています。特に、実務経験を積みやすい環境やOB・OGのサポートがある大学は、合格実績が高まる傾向にあります。
専門学校・予備校別での合格率と特徴 – 講座ごとの実績と学習スタイルの違い
専門学校や予備校では、各校独自のカリキュラムやサポート体制を整え、短期間での合格を目指す受験生にも強く支持されています。特に製図試験に特化したコースや模擬試験、個別指導が導入されている講座は合格率が高い傾向にあります。
| 学校・予備校名 | 合格率(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 大手資格予備校A | 25.0 | 個別指導・模試充実 |
| 専門学校B | 20.5 | 製図対策特化型 |
| 通信教育C | 15.8 | オンライン学習中心 |
製図試験合格率においても、講座を受講した場合と独学の場合で10ポイント以上の差が出るケースもあります。忙しい社会人から学生まで、多様な学習スタイルに合わせた指導法が選択肢となっています。
受験者の平均年齢・職業・受験回数からみた合格への道 – 多角的なデータ分析
一級建築士試験の受験者は、20代後半から30代前半の社会人が中心ですが、最近では働きながら挑戦する30代後半から40代の受験生も増加しています。合格までの平均受験回数は2回以上となる場合が多く、継続した学習が求められます。
受験者属性例
-
平均年齢:約34歳
-
主な職業:建設会社・設計事務所勤務、ゼネコン技術者
-
初回合格率(ストレート合格)の割合:約12~15%
多くの受験生が複数回受験しながら知識を積み重ねて合格を目指しています。また、職務経験や学習時間の確保が合格へのカギとなり、効率的な勉強法と計画的な受験準備が不可欠です。年齢や職業を問わず挑戦できる国家資格であることも、この試験の大きな特徴です。
一級建築士試験で合格率を上げる学習法・独学vs予備校比較 – 効率と実績に基づく選択肢解説
一級建築士試験は、合格率が例年10~15%台とされており、非常に狭き門です。受験者の多くは学科と製図という二つの関門を突破する必要があり、効率的な学習と戦略的な教材選びが重要です。独学と予備校・通信講座のどちらが自分に合った方法なのか、過去の実績や合格率を参考に選択するのが成功のカギとなります。
独学での合格率と勉強方法のコツ – 合格者のリアルな体験談を踏まえたアドバイス
一級建築士試験を独学で目指す場合、合格率は全体平均よりやや低くなる傾向があります。しかし、独学による合格者の多くが共通して重視しているポイントがいくつか存在します。
-
公式過去問題集を繰り返し解くこと
-
学習計画を早期に立てる
-
ノート作成やアウトプット学習を活用する
独学合格者からは、「時間の制約を自分でコントロールできる」「費用を抑えやすい」といった声が多く聞かれます。逆に、最新傾向や製図指導で悩むというケースもみられます。自分の理解度や苦手分野を的確に把握する工夫が、独学成功には欠かせません。
主要予備校・通信講座ごとの合格率比較と特徴 – TAC、総合資格、日建学院、スタディング等
大手予備校や通信講座は、最新の出題傾向分析・専任の講師陣による指導が強みです。過年度のデータをもとに合格実績と特徴をまとめました。
| 予備校・通信講座 | 合格率 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| TAC | 20~25% | 模擬試験と丁寧な個別指導、全国展開 |
| 総合資格学院 | 30%前後 | 合格者の体験談が豊富、添削・個別サポート充実 |
| 日建学院 | 25%前後 | 独自カリキュラム、映像講義が好評 |
| スタディング | 非公開(多数の合格者報告あり) | スマホ対応、コスパ重視の独学サポート |
独学の1.5倍~2倍近い合格率を示すケースもあり、効率的な学習や最新の傾向対策を重視する方に選ばれています。
学科試験と製図試験の学習時間配分と効果的勉強法 – 合格率向上につながる具体策
一級建築士試験の合格を目指すには、学科と製図の両方に計画的な学習時間を配分することが必須です。
-
学科試験の目安学習時間:600時間~900時間
-
製図試験の目安学習時間:300時間~400時間
学科は暗記や基礎知識の理解が中心で、効率的な過去問演習と定期的なチェックテストが効果的です。製図は実践演習が重要で、合格者の多くが「添削指導」や「実際に課題を描く反復練習」を重ねています。
スケジュール例としては、学科対策をおよそ6か月、製図対策を3~4か月確保し、早期に苦手分野を洗い出して集中的に強化することが推奨されています。学科合格後の製図対策にも余裕を持たせることで、総合的な合格率アップにつながります。
このような取り組みが、複雑化する試験にしっかりと対応し、確実な合格を目指すポイントとなります。
一級建築士試験の難易度分析と他資格との比較から合格率を考察 – 独自視点で見る試験の「狭き門」度
一級建築士試験での難易度の実情と「やめとけ」説の背景 – 合格率だけでは分からない難しさ
一級建築士試験は建築関連資格の中でも特に高い難易度を誇り、直近の合格率は約16~18%と非常に低い水準で推移しています。学科と製図の両方をクリアする必要があり、特に初回受験者の合格はさらに狭き門です。受験者の多くが複数回のチャレンジを経て合格しているのが現状で、ストレート合格率は約5%前後とも言われています。
「やめとけ」という意見も見られるほど試験対策には労力が必要です。理由は、試験範囲が広大で構造・設備・施工・計画・法規と多岐にわたり、インプット・アウトプットのバランスや時間管理が問われるためです。また、受験資格として大学や実務経験が必要なこともハードルとなっています。
多様な建築関連資格の合格率比較 – 1級・2級建築士、施工管理技士、技術士の違いと立ち位置
建築士資格だけでなく、他の建築関連資格との難易度や合格率を比較することで、一級建築士資格の位置づけが分かります。
| 資格名称 | 直近合格率 | 主な受験資格 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 | 16~18% | 学歴+実務経験 | 建築業界で最高峰の国家資格 |
| 二級建築士 | 25~30% | 指定学科卒業等 | 中小規模建築物で活躍 |
| 1級建築施工管理技士 | 30~40% | 学歴+実務経験 | 現場管理・工事監理 |
| 技術士(建設部門) | 約10% | 実務経験 | 技術士法に基づく最難関 |
この表から、一級建築士は二級建築士や1級施工管理技士に比べて合格率が低く、専門的知識と実務経験、計画力が総合的に問われることが分かります。そのため、業界内での評価や希少性も高くなっています。
難易度ランキングと業界での評価 – キャリア形成における認識と価値
一級建築士は業界での評価が非常に高く、大規模プロジェクトや設計の責任者など幅広い仕事の幅が広がります。求人市場や年収ランキングでも上位に位置し、40代の平均年収は700万円台以上とされています。スーパーゼネコンや設計事務所、官公庁などで活躍する専門職の象徴的存在です。
取得までの平均年数は3~5年ほどかかることも一般的で、合格者は「勝ち組」と呼ばれます。一方で、近年は大学ランキングによって合格率に違いがあることや、学科別に得点バランスが求められるため、効率的な学習戦略も重要です。二級建築士や施工管理技士とのダブルライセンス取得者も増加しており、キャリアアップ・独立開業を目指す方にとっても有用な資格です。
合格率に関するよくある質問を深掘り解説 – 試験合格までのリアル情報集約
一級建築士試験で合格率が低い理由と対策のポイント
一級建築士試験の合格率は例年10%台後半と、国家資格の中でも非常に低い水準です。この背景には、学科・製図ともに専門的かつ実践的な知識と設計力が問われ、単なる暗記や過去問対策だけでは通用しない点が挙げられます。特に製図試験では、実務経験を反映した設計課題の対応力が求められます。対策のポイントとしては、過去問演習と解答内容の検証だけでなく、専門学校や講座の活用も効果的です。
下記に合格率の推移と主な対策の比較をまとめました。
| 年度 | 学科試験合格率 | 製図試験合格率 |
|---|---|---|
| 2022年 | 16.7% | 39.5% |
| 2023年 | 17.4% | 41.2% |
| 2024年 | 16.5% | 40.0% |
ポイント
-
独学よりも講座利用者の合格率が高く、反復学習とアウトプット重視がカギ
-
科目ごとの合格基準点を把握し、苦手分野を早期克服することが重要
ストレート合格率・平均受験回数・合格者一覧の探し方
一級建築士試験のストレート合格率はおよそ4~5%とされ、ほとんどの受験者が複数回の挑戦を経て合格にたどり着いています。平均受験回数は2~3回以上が一般的で、年齢・職歴を問わず着実な学習継続が求められます。
合格者の詳細情報を確認したい場合は、試験主催団体による「合格者一覧表」や発表資料をチェックしましょう。大学別・都道府県別の合格状況データも公表されることが多く、出身大学ランキングや地域ごとの合格傾向も把握できます。
主なチェック方法
-
公的機関や試験団体の公式サイトで最新年度の合格者一覧表を閲覧
-
大学別・都道府県別のデータは実績として進路選択や転職の参考にも活用可能
合格発表日や試験日、受験資格に関する基本情報の整理
一級建築士試験は例年、学科試験が夏(7月)、製図試験が秋(10月)、合格発表は年末頃(12月)に行われます。スケジュール管理は合否を左右するポイントとなるため、毎年の公式発表日を必ず確認しましょう。
| 区分 | 日程(目安) |
|---|---|
| 学科試験 | 7月上旬 |
| 製図試験 | 10月上旬 |
| 合格発表日 | 12月下旬 |
受験資格は一定の実務経験を有することや、所定の学校卒業など複数パターンがあります。詳細は毎年改定される場合があるため、必ず最新の受験要項を確認してください。
主な受験資格ポイント
-
大学・専門学校の建築系卒業+指定年数の実務経験
-
二級建築士の資格保有+追加実務経験
試験欠席や再挑戦の際の手続きと注意点
やむを得ず試験を欠席した場合や、不合格となった場合でも、再受験が可能です。ただし、手続きや有効な科目合格の取り扱いには注意が必要です。学科試験を一度合格すれば、一定期間(通常2年間)製図試験の受験資格が維持されます。
欠席の場合の留意点
-
欠席申請は事前に行い、今後の受験スケジュールを確認
-
次年度再受験には再度申込手続きと受験料の支払いが必要
再受験時のポイント
-
科目合格・一部免除制度の有無を必ず確認
-
前回の不合格原因をしっかり分析し、弱点強化に重点を置いて学習Planを立てると効果的です
合格率データを活用した効果的な受験計画と合格後の展望を紹介 – 戦略的な活用法の提言
合格率を踏まえた学習計画立案の具体例 – 科目別・学習期間別の目標設定
一級建築士試験の合格率は近年16%前後で推移しており、全国の受験者にとって非常に高いハードルとなっています。この合格率を目安とし、合否を分けるのは効率的な学習計画です。習得が難しい構造や設備科目は重点配分が求められる一方、確実に得点できる学科や施工もバランスよく学ぶことが重要です。週ごとの進捗管理や、月逆算型の目標設定によって得点率の底上げが期待できます。
科目別・学習期間別目標設定例
| 科目 | 目標達成率(%) | 推奨学習期間(週単位) |
|---|---|---|
| 計画 | 80 | 3 |
| 環境・設備 | 75 | 4 |
| 法規 | 70 | 5 |
| 構造 | 70 | 6 |
| 施工 | 80 | 3 |
また、ストレート合格率にこだわる場合は、過去問題演習20年分の反復と、弱点科目の優先克服が必須です。自分の進捗を数値で確認し、合格率推移に沿って軌道修正することが合格への最短ルートです。
合格後のキャリアパスと実務への活かし方 – 一級建築士免許活用の道筋
一級建築士に合格すると、年収やキャリアの選択肢が大きく広がります。大手設計事務所やゼネコンへの就職・転職、独立開業、さらには大学・官公庁への進出など、幅広い道が開けます。年収の目安としては40歳で600万円前後、スーパーゼネコンでは年収1000万円超も珍しくありません。
主なキャリアパス
-
大手設計事務所で主任・管理職コース
-
ゼネコン設計部門・施工管理
-
独立起業による設計事務所開業
-
まちづくりコンサルタント、官公庁技術職
-
教育・研究機関での活躍
一級建築士は人生が変わる国家資格と言われ、さまざまなプロジェクトの中心として活躍できます。仕事の幅と年収・評価ともに大きく向上するため、合格後のプランニングも重要視しましょう。
試験データの今後の動向と業界展望 – 合格率から読み解く試験運営の方向性
今後の一級建築士試験はデジタル出題や科目再編などの変化が見込まれており、試験運営側も実務の即応力や創造性重視へシフトしています。合格率は今後も高水準で推移する見込みですが、大学での建築教育との連動や、受験生全体のレベル底上げも期待されています。
試験運営の転換点
-
CBT試験などのデジタル化
-
学部・専攻別合格率や地域差の公開強化
-
実務経験を活かした出題内容の増加
これからは学科の知識だけでなく、製図や設計力、法令解釈力がより一層問われる傾向が強まるでしょう。合格率推移の分析から将来の傾向を予測し、早期対策を講じることが合格とキャリアの成功への鍵となります。