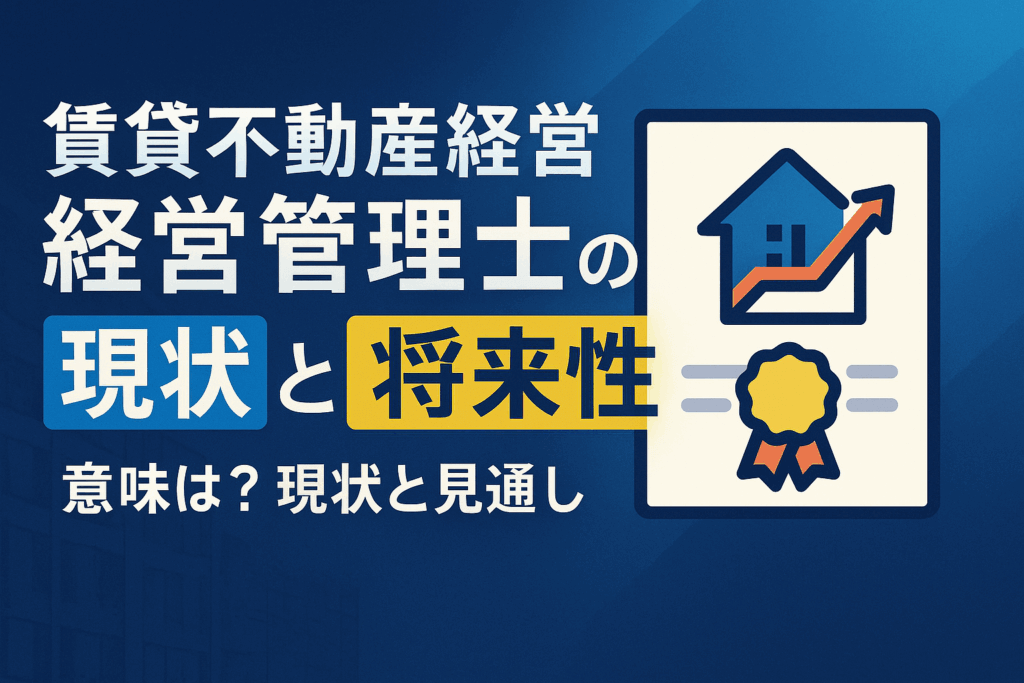「賃貸不動産経営管理士って本当に意味がない資格なの?」
そう感じて、インターネットのネガティブな声に戸惑っていませんか。
現場での実用性や求人での評価、資格が国家資格化されたにもかかわらず独占業務がないこと――【2024年度時点での合格率は約29.2%】と、決して誰でも取れる資格ではありません。それでも、宅建士と業務内容が重なる点や、求人票で「歓迎」と記載される割合が全国平均で2割未満にとどまるなど、「本当に役立つのだろうか」という疑問を多くの方が持っています。
一方で、【2024年以降、主要都市圏では管理業務主任者の設置義務が進む】など、制度や現場のニーズも年々変化。
法律の改正や不動産業界の構造変化がこの資格の価値を大きく左右しています。
実際に資格手当や年収アップに繋がる求人事例も増えており、活用の仕方次第でキャリア形成や将来性にダイレクトな影響を与えています。
「宅建士との違いは?」「学習法や独学は意味があるの?」――そんな疑問に、実体験や最新データを交えて網羅的に回答します。
この先を読み進めれば、現状の課題から将来の展望、正しい資格活用法まで、専門家ならではの視点で具体的なヒントが得られます。
「悩んだまま放置」するのは、将来の選択肢を自分で狭めてしまうかもしれません。今のうちに、あなたにとって本当に価値ある選択を見つけてみませんか?
賃貸不動産経営管理士は意味ないのか?資格の現状と批判の背景を深掘り
賃貸不動産経営管理士は意味ないと言われる主要理由
賃貸不動産経営管理士が「意味ない」と言われる主な理由には、独占業務がない点や宅建士との業務重複があります。実際に、賃貸物件の管理に関しては宅地建物取引士で対応が可能なため、資格取得後の具体的な活躍シーンが想像しにくいというユーザーの声も多いです。また、求人市場でも「必須」とする企業が少なく、評価や手当の面でも期待より低いケースがあります。以下は主な疑問とその実情をまとめたものです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 独占業務の不在 | 資格取得者だけができる業務がほとんどない |
| 宅建士と重複 | 賃貸借契約業務は宅建士でも十分に対応できる |
| 求人市場での価値の不透明 | 求人票の要件・手当基準が全国で統一されておらず価値が見えにくい |
| 転職など将来性に対する疑念 | 資格所持=キャリアアップに直結せず将来性不安の声が多い |
資格の持つ意味合いや役割自体は確立しているものの、実務でどれほど役立つかについて疑問を抱く方が多いのが現状です。
独占業務がないことの制度的意味と実務上の影響
賃貸不動産経営管理士は制度上、国家資格化されたものの、宅地建物取引士のような厳格な独占業務がありません。これにより、管理業務主任者としての手続きや賃貸住宅管理業登録に関する業務が主となりますが、日常的な管理業務は有資格者でなくとも遂行可能です。実際の現場では、資格取得による昇格や手当増額に直結しないことが多く、業務上の「必須資格」と感じにくいことが指摘されています。
主な影響点(ポイントとして整理)
- 管理会社による資格手当の有無が会社ごとに異なる
- 資格保持が必須でない企業が大多数
- 複数名の設置義務がある現場も職場によっては皆無
一方で、今後法改正や制度変更で【設置義務】が拡大すれば実務での位置付けが高まる可能性があります。現状では活用の幅が限定されていることが、「意味ない」と感じられる主要な背景です。
宅建士資格との違いと連携関係
賃貸不動産経営管理士は宅建士と混同されがちですが、根本的な違いとそれぞれの役割を正しく理解することが重要です。下記の表で両資格の主な違いを整理します。
| 項目 | 賃貸不動産経営管理士 | 宅地建物取引士 |
|---|---|---|
| 管理業務の独占性 | 一部登録業者で設置要件 | 独占業務あり(契約重要事項説明等) |
| 対象業務 | 賃貸管理全般 | 賃貸・売買等不動産取引全般 |
| 法制度の特徴 | 2021年から国家資格化 | 国家資格(長年の歴史) |
| ダブル受験・5問免除 | 宅建士所持者は一部免除あり | ダブル受験可能 |
| 手当・待遇 | 会社による | 業界全体で高評価 |
特に「宅建一本化」の話題や「宅建士ルート廃止」など制度面の変化が時折取り沙汰されていますが、2025年時点では両資格には明確な役割分担と関連が存在します。指定講習や試験日・会場などの最新制度にも注意が必要です。
今後の法改正・制度変更が資格価値に与える影響
近年、「賃貸住宅管理業法」などの法改正が進み、2025年には資格保持者の設置義務の拡大や、実務要件の厳格化が見込まれています。これにより管理会社における管理業務主任者の必要性は高まる可能性があります。
-
2025年以降は登録業者に一定数の有資格者設置が必須になる動き
-
資格内容や講習の見直し、過去問やテキストの刷新も進行
-
将来的には宅建士との棲み分けがより明確になる展望
今後の法的変化を注視しつつ、現時点で感じられる「意味ない」という評価がどのように変化していくかが重要です。最新のテキストや過去問の動向、推奨する勉強法にも今後ますます注目が集まります。
過去問やテキストは意味ないのか?効果的な試験対策と学習法の徹底指南
過去問活用の実態と「過去問は意味ない」という誤解の分析
賃貸不動産経営管理士の試験対策として、過去問が「意味ない」と感じる声もありますが、これは誤解です。実際、多くの受験生が過去問演習を通じて合格を勝ち取っています。過去問には、頻出テーマや出題傾向をつかむヒントが多く含まれています。特に、年度ごとの問題を繰り返し解くことで、法律や管理業務の重要ポイントが整理されるメリットがあります。一方で、過去問だけに頼ると新傾向問題への対応力が不足する可能性があるため、最新の法改正や追加されるテーマにも注目が必要です。正しい使い方を理解することで、試験本番の得点力を着実に伸ばすことができます。
過去問から読み解く出題傾向・頻出テーマの攻略ポイント
近年の出題傾向を見ていくと、管理業務、契約実務、法改正に関する内容の出題が目立ちます。また、独占業務や設置義務など直接業務に関係するテーマが繰り返し問われているのも特徴です。ここで得点を伸ばすためには、以下の観点が重要です。
-
主な頻出分野
- 管理業務(賃貸住宅管理業法、重要事項説明)
- 建物・設備管理
- 法改正対応
- 独占業務と設置義務
-
効果的な対策法
- 過去3~5年分の本試験問題を繰り返し解く
- 不明点をテキストや講座で確実に復習する
- 新傾向問題には市販模試や予想問題で対応力を強化
このように、出題傾向と自分の弱点を意識した学習が合格への近道となります。
おすすめのテキスト選びと独学・通信講座利用のポイント
賃貸不動産経営管理士の対策テキスト選びでは、信頼性と最新情報の網羅を重視する必要があります。市販テキストは、ランキングや口コミを参考に選ぶことで、効率的な独学が可能です。また、「テキスト おすすめ」や「テキスト 無料」などのワードで探すと、出版社公式サイトでサンプルや無料講座を確認できることもあります。独学の方は自分のペースで進めやすい一方、最新法改正や毎年の出題傾向を捉えにくい場合があるため注意が必要です。
通信講座は、解説動画や模試、個別フォロー体制が整っており、時間が限られている方にとって強い味方となります。以下は主要な学習方法と特徴です。
| 学習方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 市販テキスト(独学) | 幅広い参考書、最新情報の見極めが鍵。価格も安価。 | 自主学習が得意、コストを抑えたい人 |
| 通信・オンライン講座 | 法改正や出題傾向の反映、個別サポート・模試などメリット大。 | 時間効率重視、着実に合格したい人 |
| テキスト+過去問集 | 出題傾向把握と弱点克服がしやすい。一問一答で知識の定着も◎。 | インプット・アウトプットを並行したい人 |
学習スタイルやライフスタイルに合わせて、自分に最適な方法を選ぶことが合格へのポイントです。独学で不安な場合は、サポートの充実した通信講座やフォロー体制のある教材を積極的に活用しましょう。
賃貸不動産経営管理士の将来性と不動産業界変化の関連性
賃貸管理業法における資格設置義務の現状と市場ニーズ
賃貸不動産経営管理士の設置義務は2021年6月の賃貸住宅管理業法施行により施行されました。賃貸住宅管理業者は200戸以上の賃貸物件を管理する際、管理業務主任者として有資格者の設置が義務づけられています。これは業界の透明性や管理サービスの質向上、入居者保護を目的としたものです。
一方で「賃貸不動産経営管理士は国家資格ではない」とする指摘もありますが、法的根拠や資格の社会的意義は拡大しています。市場の賃貸ニーズが高まる中、企業や賃貸オーナーからの管理士への期待も上昇傾向です。設置義務対象の会社数やニーズは全国的に増えており、資格保有者の求人も都市部を中心に拡大しています。
テーブル:設置義務と現状
| 対象業者数 | 設置義務の有無 | 市場ニーズ |
|---|---|---|
| 200戸未満 | 任意 | 比較的低い |
| 200戸以上 | 義務 | 非常に高い |
「賃貸不動産経営管理士 意味ない」との声もありますが、物件管理のプロフェッショナルとして、今後の不動産市場に欠かせない存在となっています。
将来的な独占業務付与の可否と業界展望
現在、賃貸不動産経営管理士には明確な独占業務がありませんが、今後の業界動向によっては状況が変化する可能性があります。不動産管理の複雑化や法規制の強化、さらに入居者の権利保護強化の流れから、管理士の役割は拡大していくと予想されています。専門機関や関係者の見解では、将来的に独占業務が付与される動きも視野に入れて議論されています。
今後想定される業界の変化としては以下があります。
-
住宅管理業務の高度化と業法強化
-
オーナー、入居者双方からの専門人材需要増
-
他資格(宅建士など)との役割分担・連携の再編
現時点では宅建士との一本化や新たな資格要件の追加は未定ですが、2025年を見据えた法改正議論が進行しています。
最新の法改正動向と資格取得環境の変化
2025年に予定されている関連法改正は、業界全体に影響を与える大きなトピックです。主な変更点として、管理業務主任者の責任範囲拡大や、報告義務の強化などが盛り込まれています。これにより、管理士の知識と実務能力がこれまで以上に重視される傾向が強まります。
資格取得を検討する方にとっては、過去問対策や最新のテキスト、実務講習の積極活用が今後の合格のカギとなります。おすすめの学習方法は下記の通りです。
- 最新テキストの活用(ランキングや発売日も確認)
- 過去問を繰り返し解く
- 独学が難しい場合は講座・通信教育を併用
また、合格後の登録や実務経験の積み重ねが年収アップや求人シーンでの優位性につながります。不動産業界でのキャリアを目指す上で、タイムリーな法改正情報に注目しつつ、計画的な学習を進めることが重要です。
資格取得の価値を示す年収・手当・求人動向リサーチ
賃貸不動産経営管理士の平均年収と資格手当の実態
賃貸不動産経営管理士の年収には地域差や企業規模の影響が見られます。平均年収は約350万円から450万円が目安となりますが、大手不動産会社や管理戸数の多い企業では500万円を超えるケースもあります。資格手当については月額5,000円から10,000円が相場です。資格取得により基本給とは別に手当が支給されることで、給与面での優位性が生まれやすいのが特徴です。
下記は年収・手当の目安を表にまとめています。
| 地域 | 平均年収 | 資格手当(月額) |
|---|---|---|
| 東京・大阪 | 400~500万円 | 8,000~10,000円 |
| 地方都市 | 350~400万円 | 5,000~8,000円 |
| 中小企業 | 340~380万円 | 5,000円前後 |
| 大手企業 | 450万円以上 | 10,000円前後 |
資格手当は、宅地建物取引士やマンション管理士など他資格と組み合わせて支給総額が増える場合も多いです。特に専門性を評価する企業ほど支給額は増加傾向にあります。
求人市場における需要傾向とエリア別事情
賃貸不動産経営管理士の求人は都市圏を中心に増加しており、「求人 東京」「求人 大阪」など主要都市での需要が明確です。大手管理会社では必須資格や優遇条件として明記されるケースも増えています。特に東京や大阪では、賃貸管理業法の改正や物件数増加の影響により管理体制の強化ニーズが高まっています。
-
求人傾向の特徴
- 首都圏・関西圏は新築物件や大型案件も多く、高待遇求人が目立つ
- 地方都市・郊外は管理戸数の多い地場企業が需給を支えている
- シニア層の再就職市場でも専門性の高さや経験値が評価されやすい
資格保有者のニーズは将来的にも安定すると予測され、不動産管理現場や人材派遣、コンサルティング会社など幅広い業種で就業先を選択できます。副業や独立開業の道も広がっています。
賃貸不動産経営管理士の実務内容とキャリアアップ事例
賃貸不動産経営管理士の業務は多岐にわたり、契約管理、建物設備のメンテナンス、入居者対応、退去時の精算やトラブル調整など、現場の幅広い知識と実務経験が求められます。さらに法改正により管理業者への資格者設置義務も強化されたため、法務やリスクマネジメントのスキルも重視されます。
主な業務例
-
賃貸住宅の契約書類チェックと更新手続き
-
入居者からの相談対応やクレーム処理
-
法律改正対応や管理責任者としての報告業務
-
資産価値維持のための建物検査・補修提案
キャリアアップ事例
-
企業内で主任・管理職への昇進
-
宅地建物取引士やマンション管理士とのダブル資格取得による専門性強化
-
独立開業や不動産投資、コンサル業への転身
実務現場では、資格があることで他のスタッフとの差別化が図れ、管理者やリーダー的ポジションを任されるケースが増えています。また、法改正が続く業界だけに、「賃貸不動産経営管理士 意味ない」とは言い切れない強い価値が現れています。
合格難易度・試験日程・受験ルートの詳細分析
難易度比較:賃貸不動産経営管理士と宅建士・他資格の違い
賃貸不動産経営管理士試験の合格率は例年20〜30%台で推移しており、宅建士(宅地建物取引士)の合格率15〜17%よりも高めです。マンション管理士と比べても取得しやすい部類に入ります。勉強時間は個人差があるものの、平均100〜200時間前後が目安とされ、宅建士は300時間〜、マンション管理士は500時間以上が一般的です。
下記のテーブルで各資格の試験難易度・特徴を比較します。
| 資格名 | 合格率 | 推奨勉強時間 | 難易度 | 独占業務 |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士 | 20〜30% | 100〜200h | 易しめ | 一部管理業務等 |
| 宅建士 | 15〜17% | 300h〜 | 中 | 宅建業全般 |
| マンション管理士 | 8〜10% | 500h〜 | 難しい | 一部管理組合業務 |
賃貸不動産経営管理士は範囲が絞られており合格しやすいものの、将来的に制度変更や独占業務・設置義務強化の動きも注目されています。
受験日・試験会場・最新の試験制度情報
賃貸不動産経営管理士試験は毎年11月中旬ごろ実施されており、2025年試験日は11月16日(日)の予定です。全国主要都市に試験会場が設けられるため、居住地に合わせた選択が可能です。また、指定講習を修了した受験者には「5問免除制度」があり、より合格の可能性を高められます。
講習や免除に関する最新情報に注意することが重要です。独学での受験も可能ですが、近年は市販テキストのランキングやおすすめ教材選びが重要視されています。公式テキストだけでなく、無料公開される過去問の活用も効果的です。試験はマークシート形式で、申込期間や受験料も毎年発表されるため、最新の公式情報を必ず確認しましょう。
ダブル受験問題点と効率的学習戦略
宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブル受験は、重複する出題範囲が多く効率の良い学習が可能というメリットがあります。特に宅建持ってる方は、勉強負担を大幅に軽減できるため短期間での合格が狙いやすいです。
デメリットとしては、試験日程が近接しているため学習計画に十分な余裕を持つ必要がある点、また賃貸不動産経営管理士の将来的な制度変更や宅建士との一本化議論が進んでいる現状のなか、両資格をどう活かすか慎重な検討も必要となります。
効率的な学習ポイントとして、共通領域を優先して着実に得点源にし、苦手分野は過去問や模擬試験、テキストを併用して繰り返し学習しましょう。両資格は不動産業界でのキャリアアップや求人市場での価値向上にも直結するため、計画的な準備と最新情報の収集が大切です。
他の不動産関連資格との詳細比較
不動産系国家資格の比較(マンション管理士・宅建士等)
不動産分野で人気の高い資格には、賃貸不動産経営管理士、宅建士(宅地建物取引士)、マンション管理士などがあります。それぞれの資格ごとに役割や独占業務、取得難易度、現場での活用範囲が大きく異なります。以下のテーブルで主要資格を比較し、違いを整理します。
| 資格名 | 役割・業務 | 独占業務 | 難易度 | 実務範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸住宅の管理業務全般 | 管理業務の一部 | 普通〜やや難 | 賃貸管理会社中心 |
| 宅建士 | 不動産取引の契約手続・説明 | 重要事項説明など | 難しい | 不動産売買/仲介/賃貸全般 |
| マンション管理士 | マンションの維持管理・運営 | なし | 難しい | 分譲マンション管理組合等 |
宅建士は国家資格で独占業務範囲が広いため不動産業界での汎用性が高く、賃貸不動産経営管理士は主に賃貸物件の管理業務に特化しています。マンション管理士は分譲マンション管理組合向けのコンサルティング役割が主となります。
賃貸不動産経営管理士と宅建士、どちらが適切かの見極め
どちらの資格取得が最適かは、どの分野・業務に携わりたいかで変わります。
-
賃貸物件の管理・運営に携わる場合:賃貸不動産経営管理士が必須
-
売買・賃貸仲介を目指す場合:宅建士が幅広く対応可能
-
両方を扱いたい場合:両資格の取得が理想的
将来的には「宅建士と賃貸不動産経営管理士の役割の一本化」や資格要件の改正なども議論されているため、業界動向を注視すべきです。職場によっては両資格保持者に手当や昇進優遇がされるケースもあるため、キャリア戦略として両方の資格取得は強みとなります。
賃貸不動産経営管理士の単独取得と宅建士併取得の相乗効果
複数資格取得には大きなメリットがあります。
- 幅広い業務領域への対応力
- 就職・転職時のアピール力強化
- 法改正や業界変化による柔軟なキャリア設計
両資格を取得することで、賃貸の管理業務から取引仲介まで不動産業界の多様なニーズに応えられます。また、講習やテキストの内容に重複が多く、効率よく学習できる点もメリットです。採用企業側も複数資格取得者に対しては高く評価する傾向があり、年収アップや役職昇進につながる可能性もあります。
-
宅建士と一緒に取得を目指す場合は、同時学習やダブル受験、過去問活用が有効です。
-
受験日や申し込み方法、指定会場などにも余裕を持って対応することが、合格・キャリアアップへの近道です。
賃貸不動産経営管理士資格を活かすキャリア形成と実務活用法
資格取得後に活かせる具体的な仕事・副業例
賃貸不動産経営管理士資格を取得することで、不動産業界でのキャリアパスは大きく広がります。主な活用先としては賃貸管理会社の業務管理者が挙げられます。法律により一定規模以上の管理戸数を持つ場合、管理業務を行う上で有資格者の設置が義務化されています。このため、管理会社では資格保持者の需要が高まっています。
不動産仲介業では、オーナーや入居者との契約書作成、建物管理、クレーム対応など多岐にわたる現場業務で専門性を発揮できます。また、管理士としての知識を活かし、家賃保証会社やリフォーム業など関連業界への転職も可能です。
副業としても、賃貸経営コンサルタントや不動産のオンライン相談サービス、シェアオフィスなど新しい分野で資格の強みが活かせます。
代表的な活躍の職種リスト
-
賃貸管理業務管理者
-
不動産仲介業の社内講師
-
賃貸住宅オーナー向けアドバイザー
-
不動産投資や副業コンサルタント
他資格(宅建士・マンション管理士など)とのダブル資格取得によるキャリアアップも注目されています。
賃貸不動産経営管理士の登録・講習・更新手続き完全ガイド
資格取得後は、登録や講習、更新手続きが必要となります。初めて合格した後は、まず登録申請を行い、法定講習を修了しなければなりません。登録時には本人確認書類と経歴書の提出が求められます。
登録が完了すると、業務管理者として正式に活動できます。しかし、登録後も定期的な講習が義務付けられ、業界や法律の最新情報を習得する必要があります。以下のテーブルで流れを整理します。
| 手続き内容 | 必要なタイミング | 主な提出物 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 登録申請 | 合格後随時 | 申請書・本人確認書類・経歴書 | 所定の費用も必要 |
| 法定講習 | 初回登録時 | 登録証・受講票 | オンライン講習も一部対応 |
| 更新講習 | 5年ごと | 登録証・更新申請書 | 業界法改正情報が中心 |
| 業務管理者登録 | 就業先決定後 | 管理会社の証明など | 所属会社を通じ申請 |
日々変化する法制度や管理実務に即応するため、講習や試験日の最新日程にも目を配ることが重要です。賃貸不動産経営管理士の価値を十分発揮し続けるためには、これらの制度を理解し、計画的な手続きを行うことが欠かせません。
利用者の声に基づくリアルな評価・Q&A形式による疑問解消
賃貸不動産経営管理士は意味ない論へのよくある質問
賃貸不動産経営管理士の資格は意味がないのでしょうか?
この資格は、不動産賃貸管理業務において法的な管理者要件を満たすために重要です。規模の大きな管理会社や、今後の法改正動向を踏まえたキャリア形成を目指す方には有効な資格です。確かに「宅建士と比べて独占業務が少ない」「設置義務対象外の小規模物件で使わない」という実情もありますが、業界内の信頼性や担当業務の幅を広げるという点で価値があるとされています。
過去問やテキストの学習に意味はありますか?
過去問の繰り返し演習や各社のテキスト活用は、合格に向けて効果的です。「賃貸不動産経営管理士 過去問 意味ない」との声もありますが、実際には出題傾向対策や重要テーマの把握に役立ちます。2025年以降もテキストの内容や難易度改善が進むため、最新の教材で計画的な学習が推奨されます。
資格の求人価値についてどう考えるべきですか?
求人掲載で資格手当がつく場合や、「管理業務主任者」と資格を併せて保有することで業務範囲・転職先の幅が広がるなどメリットも大きいです。特に都市部(東京・大阪など)の求人市場では専門人材ニーズが高まっています。
宅建や他の国家資格との違いは何ですか?
宅地建物取引士(宅建士)は不動産取引に不可欠ですが、賃貸不動産経営管理士は管理実務に特化しています。独占業務や資格の設置義務が求められる場面は今後拡大の動きもあるため、ダブル受験や将来の一本化を見据えた取得も有効です。
下記の表で疑問や比較項目を整理しました。
| 質問 | 回答ポイント |
|---|---|
| 賃貸不動産経営管理士は必要なのか | 管理業界での必須資格化が進み、信頼・役割拡大中 |
| 過去問・テキストでの学習は実用的か | 合格力向上に必須。特に最新版テキスト活用が効果的 |
| 資格の求人価値・手当はあるか | 都市部求人増、手当支給例あり、転職有利 |
| 宅建・管理士の違いや併願はメリットあるか | 役割・業務対象が違うため、ダブル資格で幅拡大 |
| 独占業務は本当にないのか | 制限あるが、法改正や業界要件で将来的に可能性あり |
受験者・保有者の生の声と成功・失敗体験談
実際に資格を取得した方の声を集めました。
-
管理会社勤務・20代男性
「宅建を取得した後に賃貸不動産経営管理士を追加取得しました。宅建だけではカバーしきれない建物管理の知識と法令対応で評価され、業務範囲も広がりました。」
-
中小管理会社・30代女性
「会社の指定で資格を取りましたが、物件オーナーから信頼を得やすくなりました。テキスト独学+過去問演習の組み合わせが合格の決め手でした。手当も毎月付与されていてモチベーションアップにつながります。」
- 副業志望者・40代男性
「副業で不動産管理に関わる際、知識の証明として重宝しました。未経験でもテキストで基礎から勉強でき、今では小規模物件管理の仕事を受注できています。」
- 管理士一本でキャリア構築を目指す20代女性
「将来の国家資格化や宅建士との資格併用を見据え、早めに取得しました。法改正の動向も常にフォローし、勉強時間は100時間程度でしたが、十分合格できました。」
このように保有者の多くが、資格取得によるスキル面・待遇面の変化に満足しています。不安や「意味がない」といった声も一定数ありますが、実際は転職・就職活動、業務領域拡大、将来への備えなどで高い効果を実感している方が増えています。資格の活かし方や仕事の探し方に迷う人も多いですが、最新情報や年度ごとの法改正、テキストランキングやおすすめ教材もしっかりチェックすると良いでしょう。